3.本書の成立経緯
簡単な成立経緯は2で述べたように、『世界論』の出版を取りやめることになったデカルトが、自分の行動原理たる自身の哲学を公表したのが『方法序説』です。具体的な実例は生前に刊行できなかった『世界論』にありますが、どういういきさつでデカルトが自身の哲学を確立させたのかを書いてあるのが『方法序説』だと思ってもらってよいでしょう。デカルト哲学の入門書だと言っていいでしょう。
『方法序説』の正式なタイトルは『理性を正しく導き、学問において真理を探究するための方法の話。加えて、その試みである屈折光学、気象学、幾何学。』です。
4.各部解説
第1部
タイトルをつけるとすれば、「デカルトの生きた時代における諸学問の考察」でしょう。第1部の冒頭では“良識はこの世でもっとも公平に分け与えられている”と書かれています。良識は理性と同じ意味で、ここでは真偽を区別する能力のことです。
引用した部分は近代民主主義の基礎とも呼ばれ、フランス人権宣言やアメリカ独立宣言に多大な影響を与えました。要は「すべての人間に真偽の判断能力である理性が分け与えられている」ことを主張したわけですが、これは当時すごいことだったのです。劣った人間と優れた人間の間に線を引く人種主義に基づく差別の入り込む余地のない素晴らしい文章です。人間に主体性と可能性があることを信じるデカルトは、本当の意味での平等を見据えてこの第1部を執筆したことでしょう。
人間が人種に関係なく、理性を平等に有しているという考え方は、デカルト以降、ヨーロッパの知識人層では当然視されるようになっていたようです。時代は少し下って、ライプニッツとカントの間に位置するドイツの哲学者クリスティアン・ヴォルフの時代には、もともとは奴隷としてわたってきた黒人哲学者アントン・ウィルヘルム・アモという哲学者がハレ大学で教授として教鞭をとった事実があります。もちろん黒人への偏見や差別も根強くあった時代ですが、理性能力を行使する点で優れた人は教授になることができたという例は一つの注目すべき事実でしょう。
ところでこの良識は、理性とも分別ともいわれるものです。この理性を哲学上の中心概念に据えたのはデカルトの功績です。デカルト以前では、神から与えられた啓示に対する信仰が先にあり、それを理解するために知性や理性が働くとされていて、キリスト教神学のもとでは、信仰の下位概念に理性があったといえます。デカルトは理性と知性はほとんど同義として使っています。哲学史上、この理性と知性を完全に分けて考えたのはドイツの批判哲学者イマヌエル・カントです。
ところでデカルトがラ・フレーシュ学院で理性を磨く学問として、文字による学問である人文学を中心に学びました。デカルトはこうした文字の学問から得られるものはあるとはいえ、そればかりやっていると現実離れした考えに陥る、と指摘します。医学や法学もまた同じような特徴を持ちますが、ただひとつ数学だけは例外である、とデカルトは言います。そしてこの数学が好きだったと回想し、世界という大きな書物を旅して、新しい学問の原理を探しに出かけます。ここで第1部は終わっています。
第2部
タイトルとして最適なのは、「方法の問題と方法の規則」。第1部は言ってみるならば、理性が万人に分け与えられていることを確認しつつ、人文学の方法だと真理にたどり着けないことをデカルトが気づいた、という人文学の否定を結論として出しました。
第1部のあと、第2部の最初の文章にいたるまでに、デカルトが経験したであろうことを少し見ていきましょう。ラ・フレーシュ学院で8年間、ポワティエ大学で1年間医学と法学を学んだあと、デカルトはオランダに赴き、ナッサウ公マウリッツの軍隊に入ります。オランダでデカルトは15か月過ごしたと考えられています。そして第2部の始まりに書かれているドイツに向かいます。
<2.デカルトの生涯>で書いているように、このオランダに滞在した15か月の間に、デカルトはイサク・ベークマンという自然学者と出会います。ベークマンはデカルトより少し年上で、やる気に満ち溢れた自然学研究者です。オランダ時代にデカルトはベークマンと数学の問題について語り合って、その後物理学の問題(物体の落下や水圧の変化)の共同研究を行います。ここでデカルトは数学を科学の基礎に据えることができることを発見します。そして数学を基軸にしてすべての学問を統一することができる、とデカルトは考えるようになったようです。この間の重要なデカルトの体験はこういったものです。
そしてデカルトは第2部にあるドイツへ向かいます。バイエルン公マクシミリアンの軍隊に入隊するのが目的でした。そして冬になって、ドイツ河畔のノイブルクの冬営地にある炉部屋で色々と思索をします。このノイブルクの炉部屋でデカルトは思索して、学問全体を根本的に改革する構想を得ることになります。
第2部では、都市の建設は多数の人がつくるより、一人の人が設計したほうが完成度は高いとデカルトは考えている部分があります。そして真理への接近もまた、一人の人間の理性によるほうが正しい方向に向かうことができると考えます。
新しい学問の方法は数学をベースに作られています。論理学や解析幾何、代数学へのデカルトの関心があって、デカルトは数学者として素晴らしい業績をあげます。デカルトの前半生は数学者としての人生だったと言っても過言ではありません。後半生になってデカルトは興味関心を哲学やほかの学問に広げていくのです。
ちなみにデカルトの数学面での業績で大きいものは、べき乗表現の発明(35のような数字の右上に方べきを表現する表現法)、x軸とy軸を用いた平面上のグラフの発明(デカルト平面と呼ばれるもので、代数学の貢献に大いに寄与し、また代数学と幾何学を結びつけて新しい代数幾何学を創始した)などが挙げられます。
デカルトは論理学、代数、解析といった三つの学問分野に注目し、それらの長所を生かして短所を克服する4つの規則をつくります。
明証性の規則、分析の規則、総合の規則、枚挙の規則がその4つの規則です。岩波版の28頁の後ろから3行目の「第一は、」から始まり29頁の7行目の「そして最後は、」からはじまる段落の終わりまでがここの規則を明示している箇所です。
現代のことばで説明すると、まず大きな問題を考えるとき、その問題を最も適切な単位に分割して問題を考えて、その各単位間の関係性を見極めて全体を説明しようと心掛け、順序正しく、抜けもれがなく、そして誰にとっても明らかであるかどうかを検証しなさい、といったことです。
こうした数学をもとにした全学問に適用できる方法論を生み出したデカルトでしたが、そうした方法論を発表するには、当時23歳だったデカルトはもっと経験とそれに裏打ちされた実績が必要だと感じたのか、ヨーロッパ中を旅した後にオランダに移り住んで研究生活に入ります。ここで第2部は終了しています。
第3部
タイトルは「方法から導き出された生きるうえでの規則」が最適。
この第3部は人生のモラルが主題です。デカルトは生きる上でも第2部で展開した4つの規則などかあはモラルは引き出せないので、仮のモラルを掲げて、それを行動準則にしてしまいます。デカルトは生きている間に出版した最後の著作『情念論』において、優柔不断が長引くほど悪いものだ、と言っている箇所があります。若きデカルトも優柔不断になるくらいなら、仮の行動準則を決めておいて、そちらに従って行動したほうがいいことを意識していたんだと思います。
非決定をさけ、幸福を得るための3つの格律は次の通りです()。
- 私の国の法律と慣習に従うこと
- 自分の行動において、できるかぎり確固として果断であり、どんなに疑わしい意見でも、一度それに決めた以上は、きわめて確実である意見であるときに劣らず、一貫して従うこと
- 運命よりむしろ自分に打ち克つように、世界の秩序よりも自分の欲望を変えるように、つねに努めること
デカルトはラディカルなことを言った人と言われていますが、①をみると政治的には至極穏健派だったということができるでしょう。宗教も生まれた国のものを守っていくほうがよいと言っています。事実デカルト自身は新教国のオランダで過ごしながら、フランスのカトリックの信仰を終生守りとおしています。
オランダでは機械論的な世界観が問題視されて、身の安全のためにプロテスタンティズムに改宗させようとされたこともありましたが、私は母国の宗教を信仰し続けるといって、改宗を拒否したエピソードもあるくらいです。
一見すると②のモラルは明証性の原理からむしろ外れています。学問的な真実は憶測や即断を避けて、明らかにする必要があります。ところが生きる上では、一度決めたことはやり通す姿勢が大事だ、というのです。一貫性をもってやれ、ということはおそらく人格と関係しているのかな、と私見ながら思います。
そして③のモラルはすべて自分の影響力を行使できる部分にまず着目して、その外のものを無理に変えようとしないことの大事さが言われていると言っていいでしょう。自分の主体性を発揮すべきなのは、まず自分のできる範囲から行う、というのが良い人生を送るうえで大事なのは間違いないでしょう。この点はストア派の哲学の影響があると思います。
第4部
タイトルをつけるならば、「形而上学の基礎たる神の存在と人間の魂の存在の証明」となるでしょう。
第4部はオランダに移り住んだころのお話からです。デカルトが生きた当時、古代の原子論が復活して懐疑論が流行していました。デカルトは懐疑論の考え方をあまりよく思っていませんでした。しかし懐疑の行き着く果てに何があるかを明らかにする必要があると信じ、懐疑を徹底的に行いました。そして出てきたのがコギト・エルゴ・スム、つまり「われ考える、ゆえにわれあり」という真理が導かれる、というのです。これを方法的懐疑と呼びます。このコギトからデカルトは形而上学や自然学の真理を導き出そうとします。
そしてデカルトは、精神は考えるだけで物質性がない、また物質は考えることができない、といいます。心身二元論の本質はここです。
その後、神の存在証明がなされます。ここでは詳しく見ませんが、神の存在証明としては11世紀の神学者のアンセルムスと近い論法だったといわれております。神の存在証明がなされた後、神がわたしの知を基礎づけていることを踏まえて、懐疑が取り除かれて、理性の明証性を担保する、というのがこの第4部の流れです。
第5部
タイトルは「自然学」が適切でしょう。物質に関する考察がここでなされています。<2.デカルトの生涯>で指摘したように、デカルトは『世界論』という著作を公刊しようと目論んでいましたが、ガリレオの有罪判決を受けてその計画を白紙にして、この『方法序説』を刊行したのでした。1633年のガリレオ断罪はそれほど衝撃的なものだったのです。
17世紀に入ってからも、異端審問は各地で行われています。1600年に哲学者ジョルダーノ・ブルーノが火刑にあい、1619年、イタリア人ヴァニーニが焚刑に処せられました。1623年に詩人ヴィオーが欠席裁判で死刑を宣告され、1624年、アリストテレスに反対した学説を唱えたビトーたちを追放刑にします。
この第5部で書いてあることは『世界論』のごく一部をわかりやすく書いたものだといっていいでしょう。理論面では二元論、物質面では機械論という性質を有しているのがこの第5部です。デカルトは現実世界の話としてこの話を扱わず、仮想世界でこういうことがあれば、という前置きをして第5部を語ります。
重要な論点は次の箇所でしょう。アリストテレスの質的概念の除去、数学をモデルとした世界論的自然界、人体、心臓の運動と血液循環、自動機械としての身体、精神の不死性。こうした事柄に対するデカルトの考察が示されています。
第6部
タイトルとしてよいのは「自然の研究と学問に対する態度と展望」あたりでしょう。デカルトは実践的な哲学と実験を重視します。イギリスの哲学者フランシス・ベーコンと同じような問題意識で第6部は語られているといっていいでしょう。
デカルトは自然や物質、身体を機械論的に見ていましたが、それは健康の医学とそのための医学の進歩を願った側面も大きかったといわれています。もう一つの実験の重視というのは、学問を公共的に用いるということとも関連し、秘密知として誰かが独占できる状況を打開するために唱えられた側面があります。当時学問は魔術的なものが多かったので、魔術的学問からの解放はデカルトの一つのテーマだったと言ってよいでしょう。
デカルトはまた軍事的なためだけに学問を用いない、という科学の倫理的側面についても少しだけこの第6部で触れています。全体的な解説はここで終了です。
次の記事
次の記事は「後世への影響とデカルトについての雑感」です。
最後までお読みいただきありがとうございました。
リンク
『方法序説』解説記事の構成は以下の通りです。
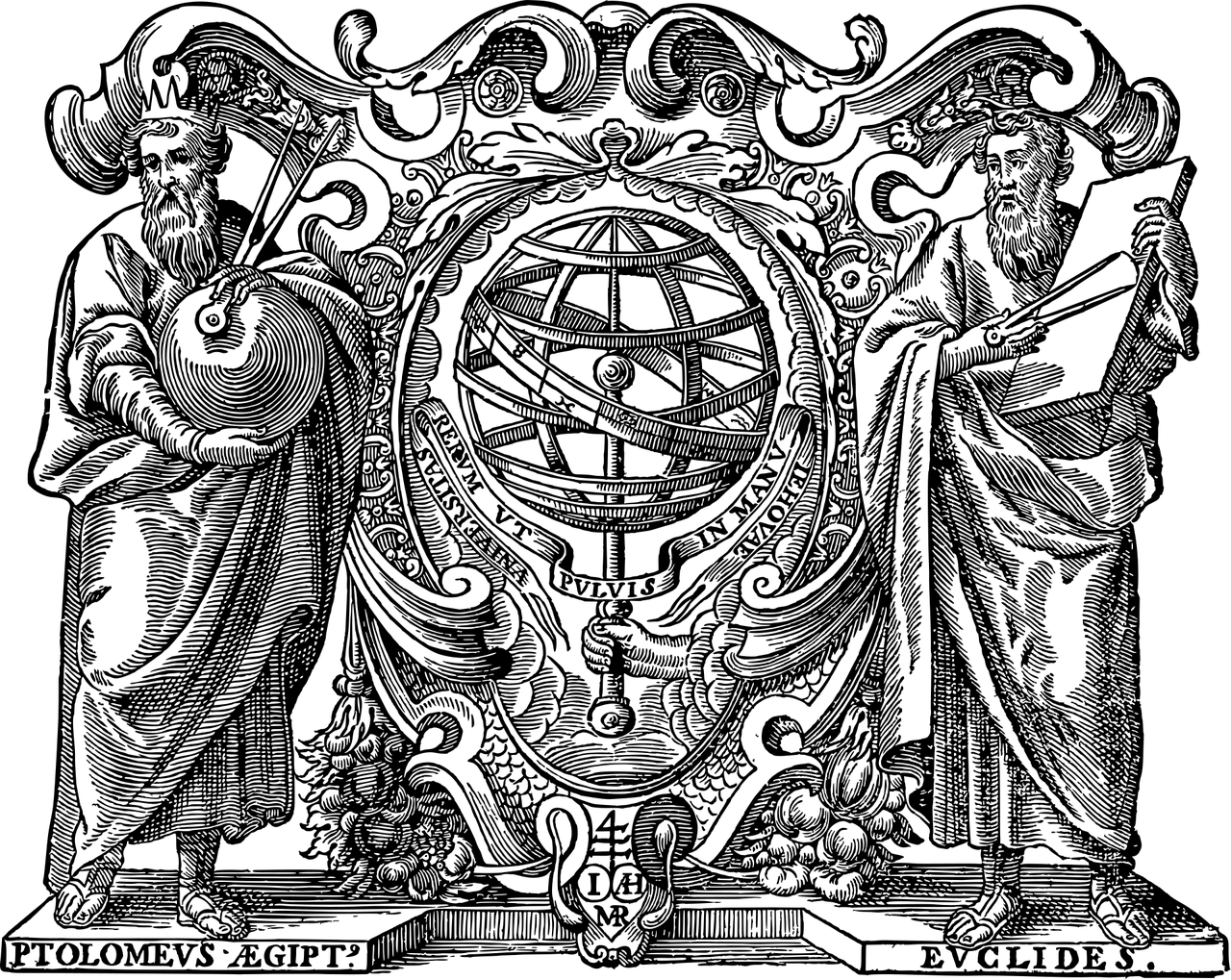
コメント