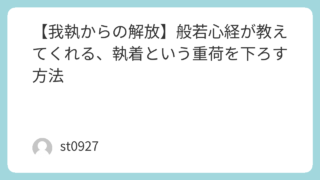 仏教
仏教 【我執からの解放】般若心経が教えてくれる、執着という重荷を下ろす方法
どうもさとやんです。前回に引き続き、般若心経に関連する記事です。最近GoogleGeminiと仏教の談話をするのですが、「私の心は私のものではないと感じることができた時、つまり心が私のコントロール下にないことを知る時、つまらないことに悩んで...
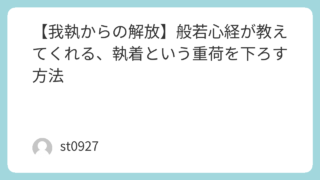 仏教
仏教 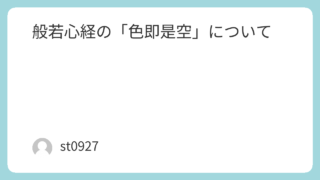 仏教
仏教  仏教
仏教  仏教
仏教  仏教
仏教  仏教
仏教  仏教
仏教  仏教
仏教  仏教
仏教  仏教
仏教  未分類
未分類  儒学
儒学  儒学
儒学 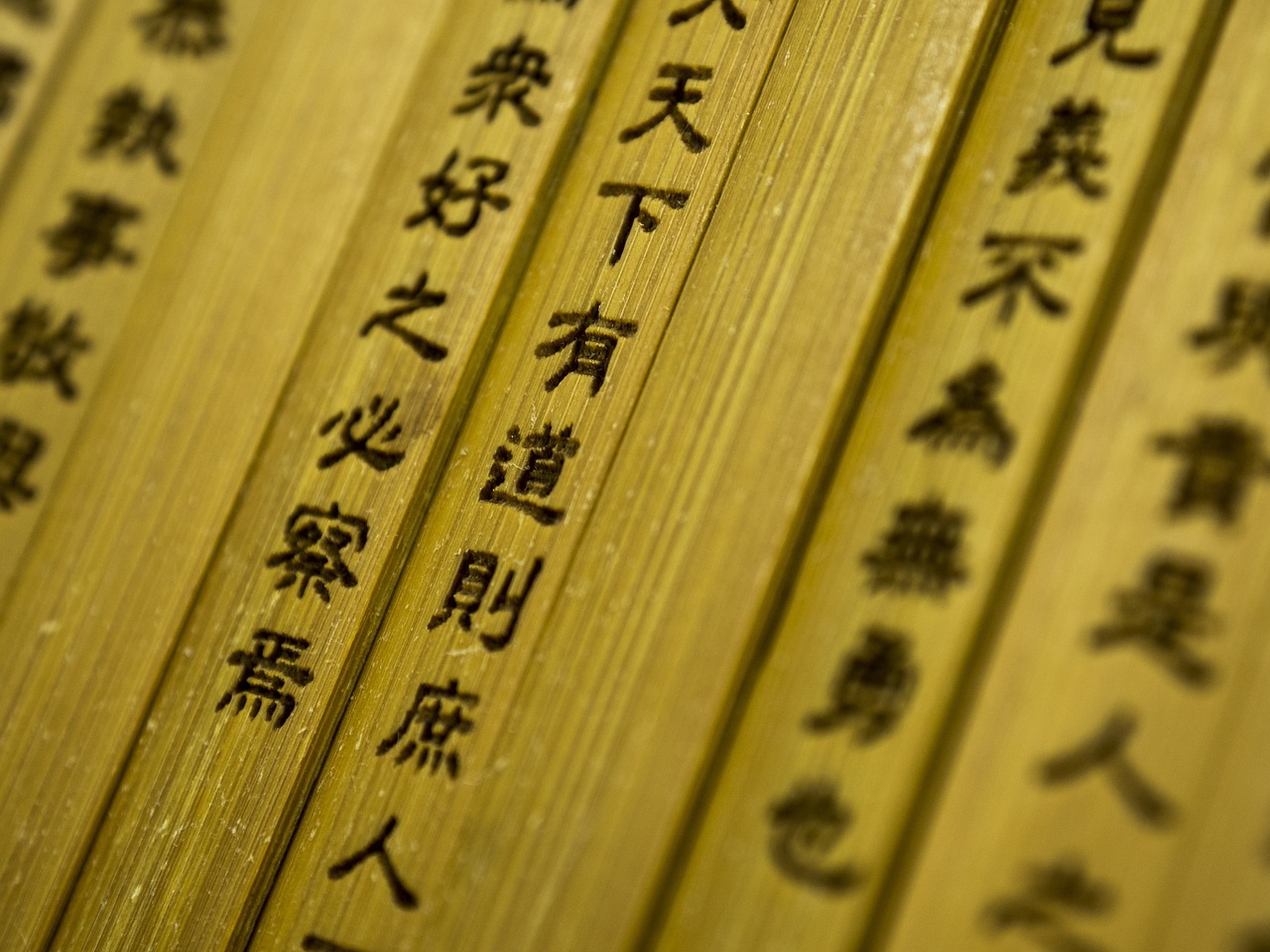 儒学
儒学  インド哲学
インド哲学