5.後世への影響と批判
ライプニッツ
デカルト哲学の問題意識を真正面から受け継ぎ、その問題点に答えようとした哲学者にドイツのライプニッツがいます。ライプニッツは二元論的世界観を受け継ぎつつ、機械論的世界論の問題点を有機論的世界論の立場から解決しようとします。主著『モナドロジー』では、無数のモナドが表象しているものが一致して、宇宙の調和と秩序があらかじめ定められている、という予定調和説を唱えました。
スピノザ
デカルト哲学の異を唱えたのが、ライプニッツと同時代のオランダの哲学者スピノザです。スピノザはデカルトの心身二元論に異論を唱え、心身平行論という一元論的世界観を打ち立てました。スピノザはその汎神論的哲学で知られ、主著『エチカ』では人間の精神や感情について論証されています。
カント
一般的に大陸合理論の祖とされるデカルトは、カントにどのような影響を与えたのでしょうか。
カント哲学のコアにあるのは、私の考えでは、認識論、その認識論に基づいた自由論です。カントの認識論は、人間が認識している現象界と人間が認識できない英知界の二つの世界があることを前提にします。人は人間の感官を通した現象を認識しているだけで、物自体は決して認識できない、とカントはいいます。物自体の世界である英知界に所属する神、世界の無限性などを理性で説明しようとしても、認識できない対象を説明しようとしているだけで、理性能力の越権行為であり、いわば理性の無駄遣いをしているだけなんだ、とカントはいいます。ところで、人間もやはり現象界と英知界に属した存在だ、と言います。現象界は自然法則に支配されて、因果の法則が延々と続く世界です。ところが英知界に属する存在としての人間は、自然法則から外れるような行為を始めることができる、というのです。これがカントのいう自由でして、人間が行為の出発点、第一原因に立つことができるという立場をカントは表明したのです。
こうした考え方の原型はデカルトの哲学にある、と私は思います。もちろんデカルトには、カントのような厳密な認識論はありません。ところがこと人間が理性的存在として自由をもつ、と考えている点に関しては、デカルトはかなりカントの立場と近いところがあるように私は感じます。デカルトの『情念論』で情念に支配されないために、謙遜などの徳を守ることを大事にして、情念を支配するために知恵をつけようとする姿勢が読み取れます。これは情念のような(因果関係に由来する)外的刺激に反応して引き起こされるものに流されずに、内的自己を保つことが自由につながるという考え方だと私は考えます。
ヘーゲル
ヘーゲルは、デカルトのことを近世の思想の英雄と論じます。デカルト哲学をもって、ルネサンスを経た哲学の夜明けが始まる、というのです。
ヘーゲルがこういうことを言うのは、神とは独立した理性をデカルトが想定したことと関係しているように私は感じます。さらのヘーゲルが自身の『精神現象学』で述べた哲学の段階としての自己意識を、デカルトが西洋社会においてしっかり確立した人物であることも関係しているでしょう。
デカルトはヘーゲルのいうような社会性を主張したことはないですが、神学のサブ学問であった哲学を独立の学問として大成させたデカルトの功績を評価している、ということでしょう。
6.デカルトについての雑感
ここには本当に私が直観的に感じたことだけを記します。
デカルトは何より人間の持つ良識を重んじた人でした。人間はすべて良識という能力をもっているからこそ、知的側面に関して人間同士に違いは一つも認められない、というのがデカルトの立場です。まさしく人を平等に見る視点を持っていたのがデカルトという哲学者でしょう。
科学的な思考法を広めたのはデカルトですが、彼は信仰と科学は両立すると信じていた哲学者です。信仰については、神の領域だから深く語りませんが、科学については人間の領域なのでこちらを多く語ったのだと思います。
デカルトは理性(良識)という能力があることを強調することで、理性的に物事を判断する力をつけた人間は主体的かつ自由に生きることができることを言った最初の人でしょう。ただ神や教会に従順であるだけではなく、近代哲学の核である自分で決めるという自律の原理が人間にはあることを言ったのです。これはスコラ哲学が支配的な中ではとてつもない進歩でした。
デカルトは西洋において、人間の尊厳性に着目した最初の近代人だということができるでしょう。
以上がデカルト『方法序説』の解説となります。最後までお読みいただきありがとうございました。
リンク
『方法序説』解説記事の構成は以下の通りです。
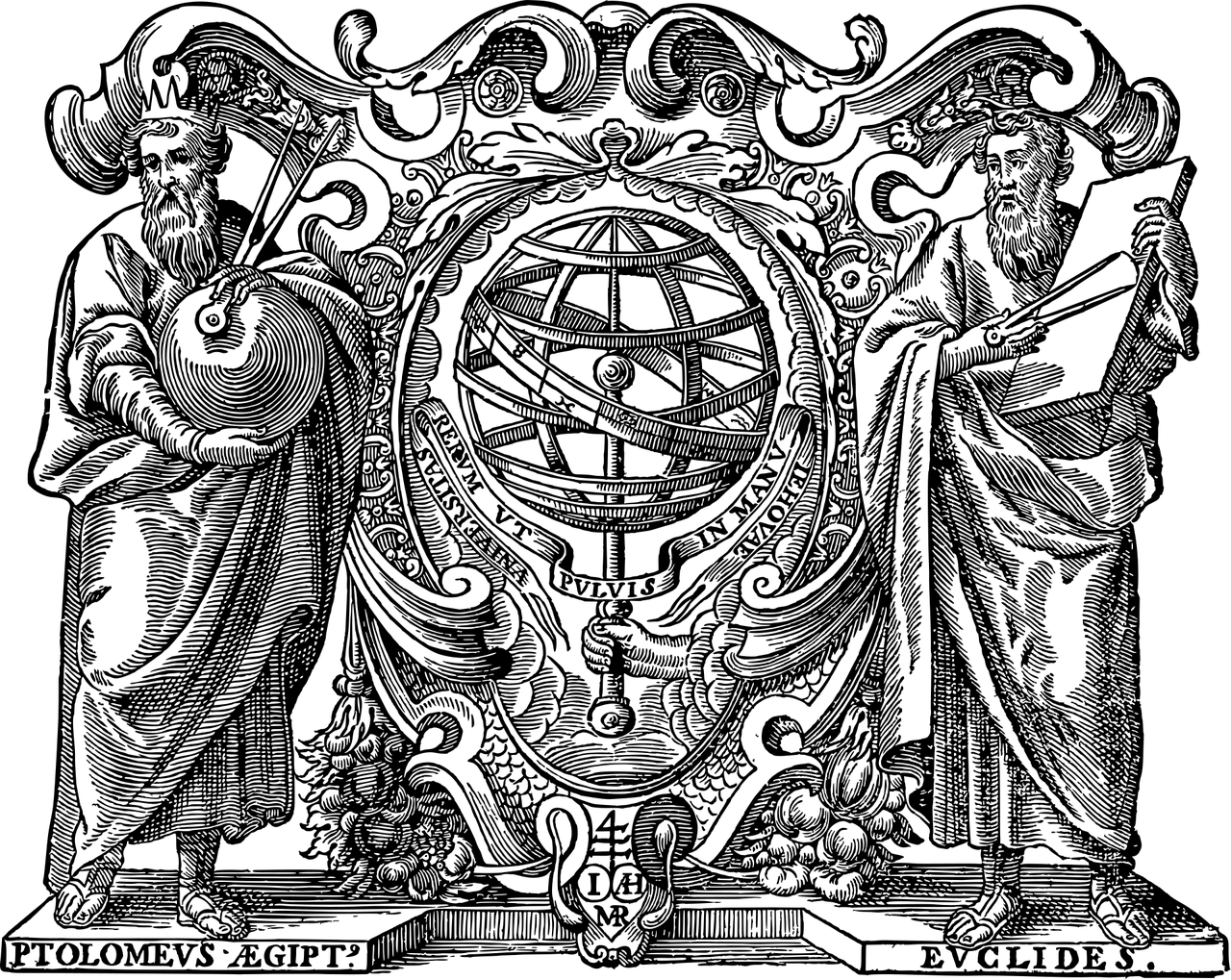

コメント