どうもみなさん、こんばんは。
高橋聡です。最近はさとやんと名乗っているので、このブログでもそう名乗ることがあるかもしれません。
6月に入りましたが、例年より雨が多く、劇的に暑い日はない印象です。梅雨が終わったら暑くなりすぎて大変そうな予感もしますが、みなさんも体調管理にはくれぐれも気を付けましょう。
さて今回は、6月3日に参加した第137回の人間塾in関西で読んだ『暗黙知の次元』(高橋勇夫訳・ちくま学芸文庫)を人間塾で出た意見も踏まえたうえで、捉え返してみたいと思います。
作者と原題について
マイケル・ポランニー
今回の人間塾での課題本『暗黙知の次元』はハンガリー出身のマイケル・ポランニーが著者です。ポランニーはもともと物理学者でしたが、のちに科学哲学者に転向しました。
兄に経済人類学者のカール・ポランニーがいます。
共産圏で科学を営んだ後、ナチスの迫害を逃れてイギリスに亡命し、大学で教鞭をとりました。
本書やその他の暗黙知に関するポランニーの研究は、現在のナレッジ・マネジメントに多大な影響を与えています。
特に野中郁次郎氏の『知識創造企業』のSECIプロセス、『ワイズカンパニー』のSECIスパイラルモデルの暗黙知という概念の形成には、ポランニーの一連の考察が与えた影響は大きいです。
原題”The Tacit Dimension”
人間塾でも出た話題ですが、本書の原題は英語で”The Tacit Dimension“です。実は直訳すると『暗黙の次元』となります。
もちろん本書は暗黙知を中心に解説した本であり、主題はまさしく暗黙知なので邦題の『暗黙知の次元』も決して間違いではありません。
しかしポランニーはおそらく暗黙知だけではなく、元来言語化できないものすべてを「暗黙の(tacit)」ということばで表現したように思えます。
tacitのほうが当然、暗黙知より広い概念です。知識の分野だけじゃなくて、言語化できない直観や感覚、あるいは受け継がれてきた技術などもtacitということばでは含んでいるのです。
つまり知識以外のものも本書の原題は問題にしているということを意識したほうがいいということでしょう。
本書でいう暗黙とは、言語であらわすことができないという意味で、つまり言語化できない領域すべてをさすことばなんです。
暗黙知は言い換えると、言語化できない知識のことで、言語になっていない経験したままの知識がこれにあたるので、経験知とも呼ばれることがあるそうです
これに関しては妥当な呼び方かな、と私自身は感じます。つまり暗黙知とは、経験したことのうち、言語的に把握していない内容が存在していることを示唆しています。
そういうことを思い浮かべながら、本書を読んでぼくが感じた本書のメッセージを各章ごとに、そして本書全体を通してのものとに分けてみていきます。
第1章のメッセージ
第1章は「暗黙知」について書かれています。
ここでのメッセージは、言語化や数式化できる知識だけが知識ではない、ということでしょう。
そうした人間が指示しようとしてもできない知識を暗黙知とポランニーは呼びます。
言語にはできないけれども、身体がおぼえているような知識、技術は暗黙知です。
科学的発見というのも実は、その学者が持っている経験知である暗黙知によって生まれるのです。
学者は暗黙知を活用して、問題が何かを明らかにして、その問題を追求し、ゴールに到るまでどのような道筋をとるべきかをイメージできるようになって、その道をまい進することで、科学的発見にいたるわけです。
明示的な(数式や言語であらわすことができる)知識の裏には、暗黙知の蓄積があるように思います。
ここでぼくが思うのは、明示的な知識は、実は莫大な暗黙知によって支えられている事実があるんだ、とポランニーは言っているのでしょう。
余談にはなりますが、そうした暗黙知を形式知に変換するために必要なことを考えるのがナレッジ・マネジメントの議論です。
第2章のメッセージ
第2章のタイトルは「創発」です。この言葉は、あまり聞きなれない単語ですね。
広辞苑によると
そうはつ【創発】
進化論・システム論の用語。生物進化の過程やシステムの発展過程において、先行する条件からは予測や説明のできない新しい特性が生み出されること。
(『広辞苑第六版』岩波書店)
とあります。少しわかりにくい表現ですが、創発とはシステムが発展して新システムが生まれると、旧システムから説明できないような原理が生まれる、ということでしょう。
つまり明示的な知識(形式知)が集まって新しいシステムが構築されると、暗黙知を蓄積して新システムの説明原理を発見する必要がある、ということでしょう。
逆に言えば、新しいシステムではこれまでの形式知が通用しない、ということでもあります。
だからこそ、言語化できない暗黙知の存在を認めて、そこに目を向けて考え続ける必要がある、といえるでしょう。
本書では物理学の対象とする物質のレベルと、生物学が対象とする有機体のレベルや無機物から構成される機械などを対象とする工学、などの例が出されています。
すべての学問はそれより小さい学問(たとえば生物学に対して物理学)の範囲の原理には則るが、その学問(生物学)の原理は前段階の学問(物理学)の原理で決して説明することはできない、ということをポランニーは説明しています。
つまりこれは明らかになった知識(形式知)をいくら寄せ集めても、より高次なシステム(高次な学問全体)は暗黙知とならざるを得ないことを言っているんだと思います。
だからこそ暗黙知をまず認識し、新たなシステム全体を見る必要があるのです。
第3章のメッセージ
第3章のタイトルは『探求者たちの社会』です。
タイトルからは何を言いたいのかよくわかりません。第3章をよく読むと、科学者が社会的に責任をどう果たしているのか、という倫理の話だということがわかります。
科学者の発見とは、一見個人的な事柄のように思えるけど、実際はそうではない、とポランニーは言います。
科学者が発見をする原点となる科学者の興味は社会的に形成されたものであり、社会とは祖先からの引き継がれた形式知と暗黙知の総体なのです。
その知の総体たる社会で科学者が責任を果たすには、まず個人がコミットメントを発揮することが必要です。
コミットメントということばは、日本語では非常にわかりにくいですが、行ってみれば計画や組織に対する参加の度合いをいうのです。
コミットメントはその計画や組織のルールを作成し、主体的な中心となって動く参加のことです。参加にはその下の段階があり、度合いが高いものからエンロールメント、コンプライアンス、アンコンプライアンスとなります。
つまり科学者は自分が発見するであろう科学的プロジェクトに全身全霊で参加し、主体的に動かないといけない、ということです。
そのことを前提として、本書のp136にこうあります。
なぜならそれは、思考は固有のパワーを持ち、隠れた真実の暗示によって人間の精神に呼び起されるものだ、という確信を伝えているからだ。それは、そうした反応ができる能力を持つものとして、個人に敬意を払っている。つまり、他の人々には見えない問題を見て、自分自身の責任においてそれを探究するという能力を持つものとして。これこそ自由でダイナミックな社会における知的生活の、形而上学的基盤なのである。それは、言い換えるなら、こうした社会における知的生活を守る原理なのである。私はこのような社会を「探究者の社会」と呼ぶ。
(『暗黙知の次元』p136)
ここは暗黙知を認めることで、科学者それぞれが自分の責任で自分の問題を探究する能力をもって、互いに尊敬しあう社会こそ、探究者の社会なのだ、ということです。
そして「探究者の社会では、人間は考えている」とポランニーは強調します。
共産主義や実存主義のように、人を考えないようにしてしまう思考体系に対して、探究者の社会では人は考えます。その事実が大事だ、ということです。
考えることをやめてしまえば、人間は何にも責任を取ることができなくなってしまう。だから人は考えないといけない。科学は考えるのに適したディシプリンだ、というのがポランニーの主張であり、メッセージでしょう。
全体のメッセージ
ポランニーはソビエトの理論的指導者であるブハーリンと話したとき、人間が考えなくさせる共産主義の問題点を痛感した、という話が最初のほうに出てきます。
同時に実存主義もまた、虚無をもとにした現実を見えなくさせて、考えずに決断を要求する無責任なドグマである、とポランニーは捉えていたのでしょう。
こうした人間を考えさせないようにするイデオロギーに対して、暗黙知を認めることで科学は人々に考える土壌を提供する、とポランニーは言いたかったんだと思います。
人間は考えることができる、それが動物との最大の差異であって、それをやめてしまえば動物的生活しかない、とポランニーは共産主義圏のゆくてをみて感じた節があったんでしょう。
また別の見方をすれば、ポランニーはドイツのナチズム的な全体主義、ソビエト的な全体主義どちらも問わず、民衆を考えさせずに飼いならす全体主義の危険性を告発したともいえるでしょう。
そういう点では、ポランニーはドラッカーやハンナ・アレントと同じような問題意識を持っていたともいえるでしょう。
だからこそ、ポランニーは人間は考えることをやめてはいけない、というメッセージを本書の全体で発しているのでしょう。
あとぼくが興味深さを感じたのは、社会的に求められたことに全力でコミットメントすることが自由だ、というような表現がありました。
自分に課せられた使命を全うするのが、人間の本当の自由への道ということでしょう。
以上、さとやんがお届けしました。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
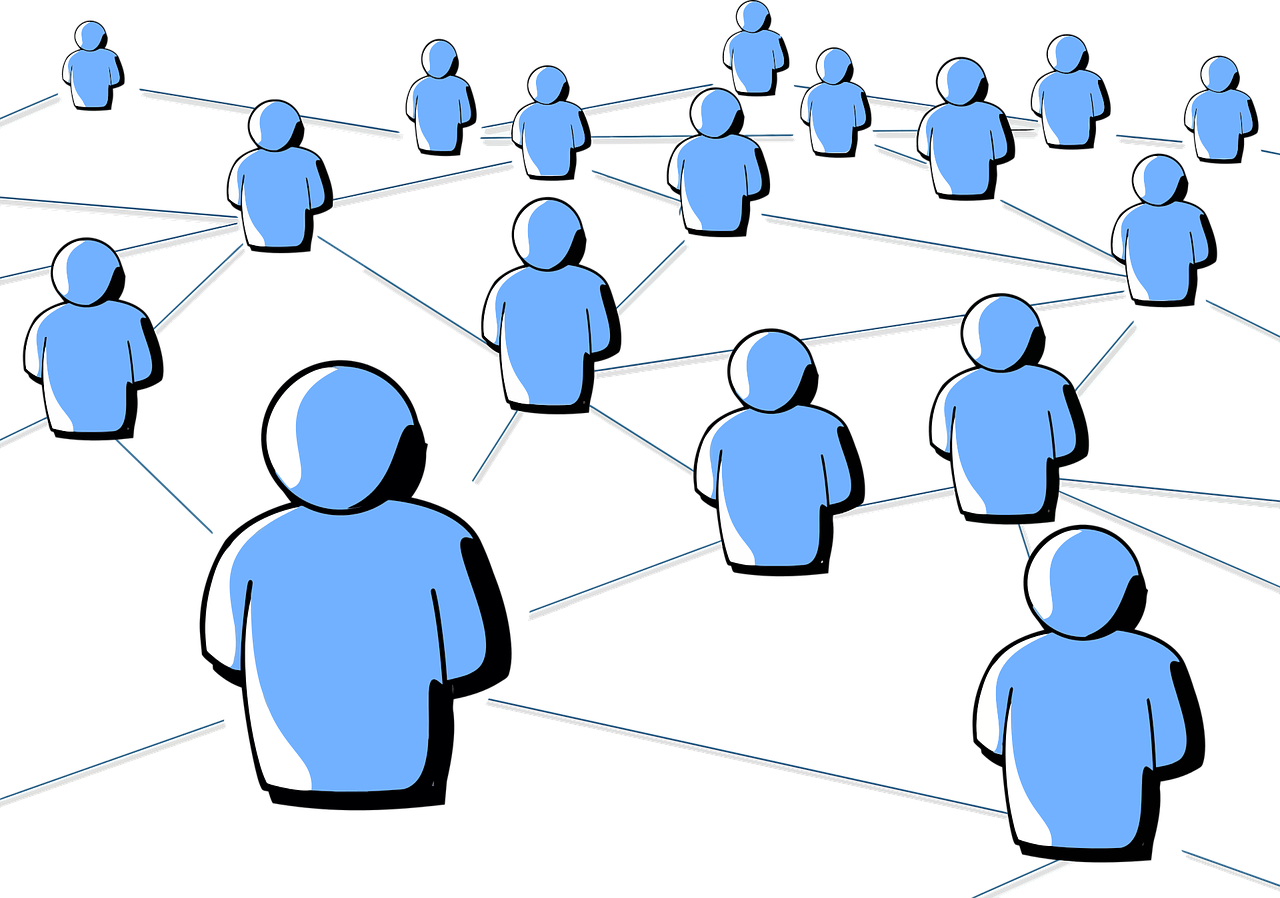

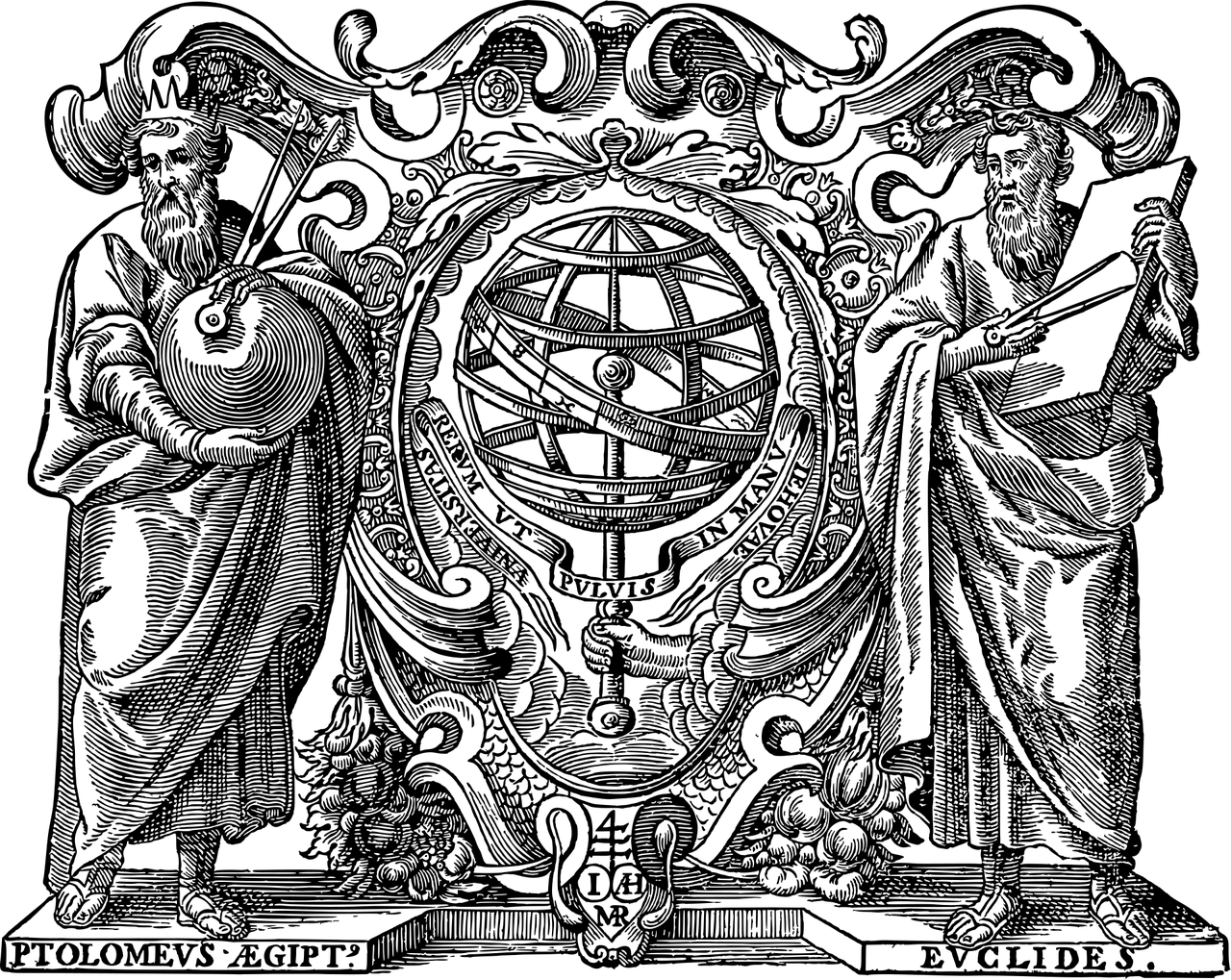
コメント