おひさしぶりです、たかはしさとしです!
どうもこんばんは、たかはしさとしです。みなさん、お久しぶりです。もう3か月以上noteは更新していませんでしたね。大阪もコロナが一気に増えていますけども、私は週三回相変わらず淀屋橋という大阪のオフィス街に通っております。コロナにかかって周りに感染させないようにはしないとなあと思いますけど、この状況だと感染してしまうリスクも考慮して行動しないといけないですね。とはいえ暗い話ばかりしていても仕方ありませんので、本題に入りましょう。タイトルにも示しましたが、この文章は一種の書評であります。『ネット文章講座』の書評をまた書きます
たとえばこの記事。あとこの記事など。
そう、さわらぎ寛子さんの著書『自分らしさを言葉にのせる売れ続けるネット文章講座』の書評です。文章術の本とはいえ、文章を書く上でのテクニックはもちろん、過剰な表現はしないことが信頼につながるなど、当たり前ながらコピーライティング界では誰も指摘しない素晴らしい内容が詰まった本だと勝手に思っております。
今日はこの本の中和剤としての側面をお伝えしたいと思います。
中和剤って何
そもそも中和剤って何でしょう。たまに耳にする言葉ですが、ちゃんと説明できる人はいますか。中学校の理科で確か習いましたよね。覚えていますか。
水酸化ナトリウムを中和する実験のときに使ったのが、塩酸でしたね。
水酸化ナトリウムと塩酸を全く同量、化合させるとできるのが食塩水でした。
<p
name=”3hh4J”>つまり水酸化ナトリウムの中和剤として塩酸を使うことで二つの液体の性質が中性となって、刺激性などもない食塩水が出来上がったんです。
一応、中和の定義をいうと酸性とアルカリ性の物質が化合されて中性になる、ということですけど、そこまで説明できなくてもOKです。
イメージとしては、プラスの性質のものに中和剤として同量のマイナスの性質のものを加えて反応させると、中和されて中性のものができるんです。
中和剤としての『ネット文章講座』
そして、『ネット文章講座』は中和剤として作用する、とぼくはいいたいんです。ここでは単なる無機質な説明文(客観的文章)と、熱い思いがこもってるけど客観性に欠ける文章(主観的文章)を一応対比しているつもりなんですね。そしてネット文章講座を読むと、無機質で面白味が少ない客観的文章に熱い思いを入れる作業を加えることができて、ちょうど主客のバランスの良い文章が出来上がるイメージなんです。これってぼくの勝手な感覚を比喩にしているだけなんです。でも意外といいように説明できた、と思っております。『ネット文章講座』の文言を借りてくると、「自分らしさ」とは主観的な思いにほかなりません。そして「売れ続ける」文章というのは相手にわかるように客観的な文章である必要があります。その二つがそろってやっと自分らしい売れ続ける文章を作成できるのです。だからどちらかが足りないと感じたときに、『ネット文章講座』を読み直して、自分の文章を見つめなおすことをおすすめします。
ブログに載せる文章が無機質になってきた
どうしてこの本を読んで主観性を注入しないといけないのか。実はぼくは何回かここにも出していますが、ブログをやっています。
それが以下のブログです。
ニーチェマニア!
人文科学系、主に哲学の専門用語の解説を中心とした雑記集
evangelist-st.com
ぼくのメディアの方向性を見なおしたときに、noteにまとめ記事などをのせて、ブログのニーチェマニア!では専門用語の解説を中心に書いていこうと分業しようとしたんですよね。そして最近ブログでは、専門用語の解説を書いておりました。
ところがどうも筆が進まなくなってきた。
こういうときは違和感を無意識ながら感じているときなんですね。
その違和感とは、客観的な文章を心がけすぎて、自分の思いがあまり入っていないということだとすぐに気づきました。
簡単に言うと、文章が無機質になってきたということです。
わかりやすさや論理性を求めすぎるあまり、ブログに載せる文章から自分の思いを排除してしまった。これはやばい。
と思い、自分に喝を入れるつもりで中和剤として『ネット文章講座』を読み直しました。
どんだけこの本を読んだときはわかったつもりでも、油断するとすぐに客観的な文章に戻ってしまう癖があることがわかりました。これが今回の最大の収穫です。こうした気づきって大事ですよね、ほんとに。
文章が主客どちらかに偏りすぎたときは中和剤として『ネット文章講座』を読もう
さいごにまとめです。文章が主観的文章に偏りすぎたり、逆に客観的文章に偏りすぎたと感じるとき、読むのにいいのが『ネット文章講座』です。どちらにせよ、ちゃんと中和剤として働いてくれる作用があるとぼくは思っております。文章を書いて違和感を感じたら、ぜひ本書を読んで方向性を確認しなおしましょう。以上、最後まで読んでいただきありがとうございました。
たかはしさとししるす
</p


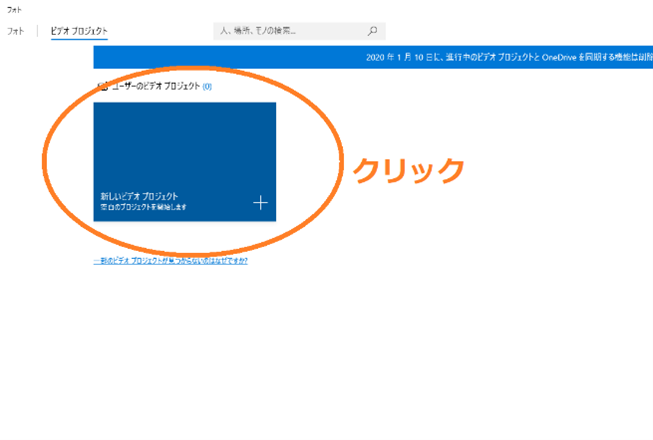
コメント